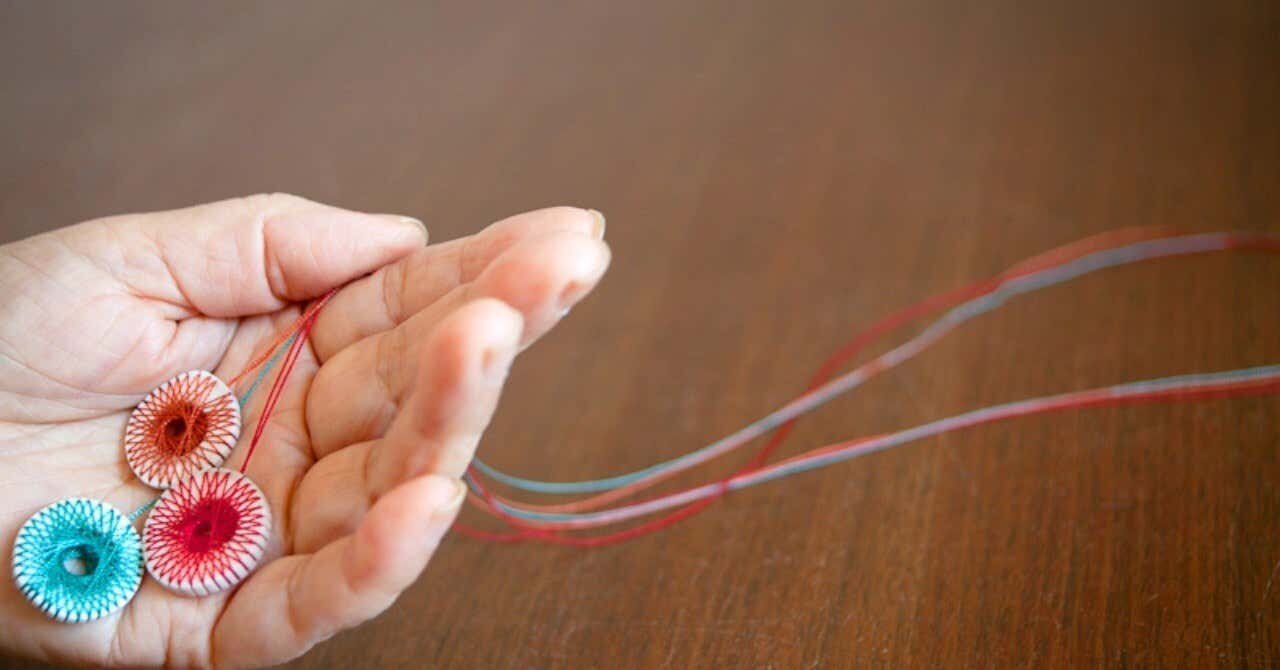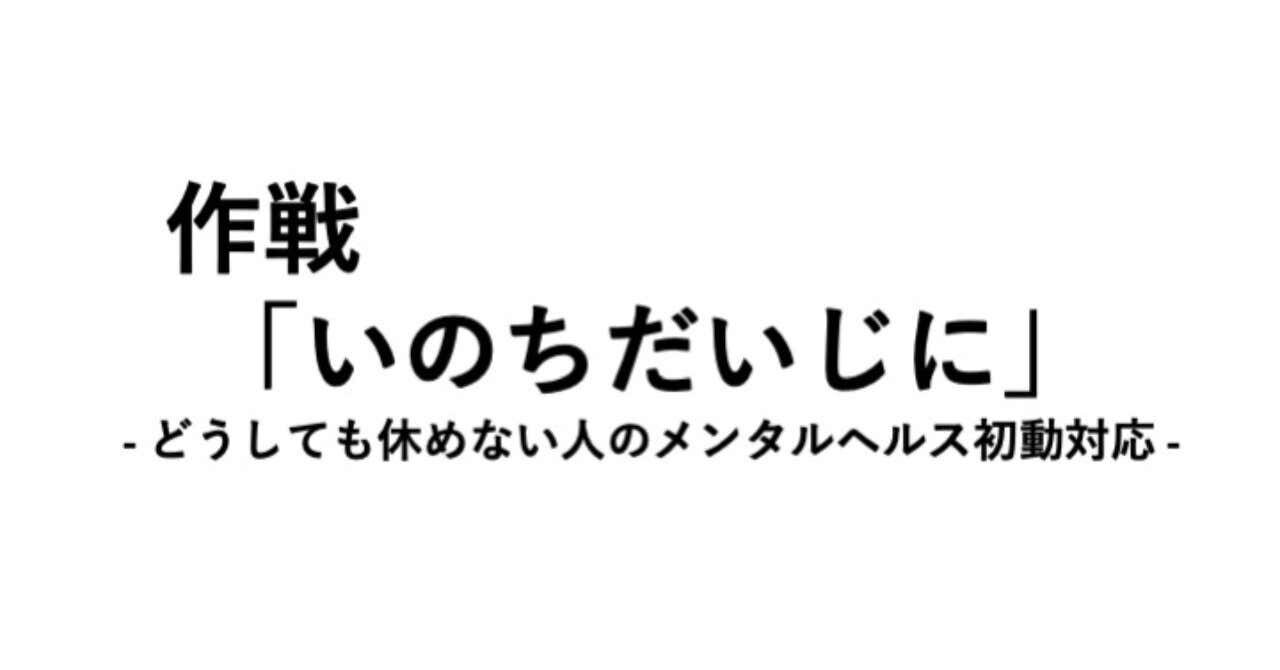1995年に地元・神戸で起こった阪神淡路大震災。当時、小学1年生だった僕は、寝室兼子ども部屋に布団を敷いて寝ており、勉強机の椅子が倒れてきて目を覚ました(と言っても、パイプのかるーい椅子だったので無傷である)。つまり僕も、当時の震災を経験した当事者である、と言えるのだが、阪神淡路の「被災経験」について、僕は語るほどのものをほとんど持たない。
Read more執筆日誌 2019/09/04
一日のこと
・メールや編集などいろいろ
・新規インタビュー2件、依頼と調整
・エニタイムフィットネス
・LITALICO研究所のチームMTG
・川崎にて面談
・立ち食いそばを食う
・久しぶりに書籍の原稿が進捗
・理事会
メモ
だいぶ涼しくなってきた。コンビニやドトールでアイスコーヒーを頼むのはいつまでだろう。
エニタイム通って運動しようとなるぐらいに心身が回復してきたのは嬉しいな。1年強経ってようやくという感じ。運動すると頭すっきりするし、この調子で執筆スピードも上がればいいが…
「ズドンとくるメッセージほど、すぐにリアクションするのは難しいから、でもじんわりと相手の心に沁みてくるもんだと思うから、慌ててフォローせず、あとはwait and hopeだと思いますね」というアドバイスをした。
Wait and hope.いい言葉だと思う。
自分の、相手の、コアの部分から目をそむけないこと。その上で、信じて待つこと。答えを急がないこと。
Yahoo!ニュースのオーサーコメントを投稿。
Yahoo!ニュースの編集部のみなさんは、文章に手を入れるという意味の編集はしないけど(オーサーが自由に執筆できる)、僕の関心やテーマを踏まえて、このニュースにコメントいただけませんかとか、こういう記事を書いてみてはどうでしょうと、色々と提案してくれる。一緒にやっていて気持ちいい方々だし、応えたいと思う。
トップアスリート特有の孤独や痛みについて、やはり取材をしたいと思う。書籍への盛り込みが間に合うかわからないが、Yahooと連動して、企画したい。
香港の逃亡犯条例撤回。
韓国文学が気になっている。
ヒグチアイさんの新譜が楽しみ。
東藤さんに教えてもらって大森靖子の「死神」を聴いた。すごい曲だ。
久しぶりに安藤さんに進捗を報告できた日。
やはり年内に出版を間に合わせたい。正念場の9月。
#子連れ会議OK の運用実態について、子育て共働き世帯の一人が思うこと
土日にムスメが熱を出したので、昨日は朝イチで保育園にお休みの連絡をし、小児科へ連れて行った。
この日はお昼にクライアントMTGが入っていたのだが、休み空け月曜に当日で病児保育はさすがに取れないだろうなぁと思っていたので、前日時点で同行メンバーにチャットで連絡をした。
僕以外のメンバーは現地に行けるし、内容的にも関係値的にも大丈夫そうだから僕はオンラインでつないでくれと依頼、ムスメと一緒に留守番しながら家から会議に参加した(幸いにして午後から病児保育が取れたので、オンラインMTGのあとはムスメを預けて仕事に行けた)。
こういう対応は初めてではなく、今のところ問題なくいっているように思う。
ふと思い出した。#子連れ会議OK ってやつあったな、と。
2017年に熊本の議会で、生後7ヶ月のお子さんを連れての議場入りを試みた議員に対して、議会から厳重注意を受けたという出来事に対して、Twitter上で著名人が #子連れ会議OK ですとハッシュタグをつけて声をあげていた。
あと、つい最近では、ニュージーランド議会の対象的な対応が話題になった。育休明けの議員がお子さんを連れて議場入りした際、自身にも3人の子どもがいるという議長が、議長席でシッター役を買って出たという。
個人的にはニュージーランド議会の対応には非常に好感を持てるし、それが議会だろうが、議事進行、つまり仕事に大きく支障がでなければ別にええやんと思うものの、熊本の話も、交渉のプロセスやもともとの会議規則の解釈など各論としては色々あったようなので、ここでは深く立ち入らない。
ただ、いち働く父親として思うのは、「議会」という、(それを特別視するのも良くないとは思うけど)一般の人からするとちょっと遠い舞台での紛糾と、それに対して著名人が「キャンペーン」的に論を張る、という構図で考えると、あまり子育て勤労世帯の実態に即した話にならないのではないかと思う。
基本的には、働く子育て世帯が、勤務時間中に(つまり建前としては子育てではなく仕事のための時間に)やむを得ない事情で子どもを連れて行きたい、という「イレギュラー対応」をどう適切にこなすかという話だと僕は考える。
(そもそも子どもを保育園に入れられないという「保育園落ちた」問題には本記事では立ち入らない。それはそれで重要な問題だとは思うが、いったん分ける)
現実的にどんな場面で子連れ仕事ニーズが発生して、実際上どう対応しているのか、我が家の事例も紹介しながら、考えるところを記す。
目次
そもそもの前提として
子どもと仕事がバッティングするのはどんなときか
やってみてどうか
そもそもの前提として
職場は仕事をしにくる場所であって、育児・保育をするのは家庭や保育園の役割である。いや当たり前なんだけど。
基本的には、「子連れ」対応を実行・許容するかどうかは、仕事の遂行に支障が出ない範囲かどうかという観点が必要だし、あくまでイレギュラー対応であって、常態化することを前提に議論することではないということを確認しておきたい。
わざわざそんな当たり前のことを言ったのは、ニュージーランドの子連れ議会の様子や、著名人の「#子連れ会議OK」キャンペーン的なものの印象が強くて「子どもが毎日会社に来ることを許容しろってことか」というような誤解が生まれるとやだなぁ、と思ったからである。
子どもの発熱時などで、他にも預けられなければ、当然親の我々がお仕事お休みして子どもを看病するわけで、「子連れ会議」や「子連れ出社」、「自宅オンライン会議」等の対応を要する事態は、個別具体的に考えると、めちゃくちゃ頻度の高いするものではないと思う。
(重ねて言うが、そもそも保育園に入れないんだぁ!という問題は、それはそれで大変なのだけど、今回は子どもを保育に出している共働き世帯の事情に絞っています。また、フリーランスや土日祝のお仕事が中心の方はまた違った事情になります。ご了承ください)
子どもと仕事がバッティングするのはどんなときか
イレギュラーが発生するのは基本的には以下の2パターンだと思う(他にもあったらコメント歓迎)
A. 子どもが元気 かつ 保育時間外の仕事が発生したとき
・保育園が短縮or休みのとき(行事があって午前で終わり、お盆、年末年始休業など)
・保育終了後の夕〜夜、土日祝に仕事が入ったとき
・集団検診等があり、保育園をお休みするとき、かつ検診後の午後に仕事が入ったとき
→こういう場合に、「子連れ会議」「子連れ出勤」のニーズが発生する
我が家の場合はだいたい以下のようなフローで対応する。
1. 夫婦の仕事予定を共有、どちらかが休み・早退で子ども見られるなら休んで対応
ダメな場合、以下のいずれかのオプションを検討
2-1. どっちも予定外せない/ずらせないなぁというときは、キッズラインのシッター予約を試みる
2-2. ツマ実家が近いので、ばーばに頼めないか相談する(ばーばもまだお仕事あるから休めるとは限らない)
2-3. 予定はあるけど子連れ対応で支障ないなと判断したときは、子連れで会議等に参加(予定の数、時間、場所、性質等で判断)
B. 子どもが発熱・疾患 かつ どうしても預けられない時
・病児保育や、病児対応可能なシッター予約を試みたが空いてなかった
・土日に発熱し、週明け月曜になってから通院・病児予約トライをするため、予定が読めない
→こういう場合は、子連れ出社は不可能なので(というかするべきではない)、自宅看病しつつ「オンライン会議」のニーズが発生する。
子どもの発熱時、我が家の場合はだいたい以下のようなフローで対応する
1. まず、病児保育の予約を試みる。預けられればハッピー
ダメな場合、次に検討するのが以下
2. 夫婦の仕事予定を共有、どちらかが休んで子ども見られるなら休んで対応
それでもダメな場合、以下のいずれかのオプションを検討
3-1. 病児対応可能なキッズラインのシッターを探す
3-2. ツマ実家が近いので、ばーばに頼めないか相談する(ばーばもまだお仕事あるから休めるとは限らない)
3-3. 休んで看病しつつ、オンライン対応可能な会議のみ参加、チャットや作業は子ども見る合間に無理せずできるだけやる
上記の通り、基本的にはどちらかが休んで対応できるならする、その他の社会資源に頼れるなら頼る、それでもダメ、かつ対応できそうなら、子連れ仕事をオプションとして考える、ぐらいの順番でやっている。
僕とツマの場合、休みにくい性質の仕事としては以下のようなものがあるので、これらとバッティングしたときに子連れ検討が発生する。
①研修講師、講演、モデレーター等のイベント登壇仕事
②リスケやおまかせができない重ための会議・打合わせ(マネージャー会議とか、決めにいく商談とか、面談とか査定とか)
③インタビュー、対談、撮影等
④出張
僕は、①③④が多くて②は昨年度より減った、ツマは①②がそこそこ入る、という感じ。
(ちなみに僕がフルタイム&パラレルワーカーでツマが時短)
やってみてどうか
幸いにして、今のところあまり問題なく対応できている。子どもがいるときは「作業」はほとんど進められないので、オンラインなり子連れなりで、半分お休みだけど1件2件会議をこなして指示を出して進められるだけでもだいぶ気持ちが楽になる(お休み明けはたまった作業を片付けることに追われるので)
ただまぁ、親にとっても子どもにとっても周囲にとっても、常態化するとしんどいなと思う。
たまの子連れ出勤は、まわりのみんなも可愛がってくれて、「福利厚生だわー笑」なんて言ってくれるのだが、毎日一緒だと色々不便も出てくるかもしれない。聴覚過敏の人も職場にはいるだろうから、職場にいるときはあまり泣かないでくれよとひそかに願いもするし、どうしても泣いてしまったときは周りのみなさんにちょっと気を遣う。
また、子連れ対応しやすいかどうかは、仕事の性質や、お子さんの様子によっても変わってくるだろう。お子さんの特性やコンディションによっては、オンライン会議でもムリ、ということもあると思う。
ただ、夫婦でできる限りの対応をした上で、部分的にちょろっと「子連れ会議」や「子連れリモート」を織り交ぜられるだけで、だいぶ対応しやすくなるし、気持ちも楽になる。大事なのは、#子連れ会議OK かどうかではなく、事情に応じた柔軟な対応とサポートをすることを、前向きに、いや当たり前にしていくことだと思う。
障害のある人の権利保障に関連して「合理的配慮」という考え方がある。抜本的なルールや環境変化というよりは、個別具体的な困りごとに対して、目的を達成するために柔軟な調整対応をするというものだ。これは、障害のある人に限らず、妊婦や子育て世帯や、家族の介護をしている人、その他さまざまな事情があって、働く場面でのイレギュラー対応を必要とする人にとっても有用な考え方と実践だろう。
そして少なくとも僕は、今の所とても「合理的」な仕事環境と仲間たちに恵まれていると思うから、こうやって少しでも広がるように発信していきたいと思っている。
anthropocene(人新世)を生きる私たちの宿題 2019/08/21
設樂剛事務所主宰、世界構想プログラム2019「生命論マーケティング」第1回。完新世から人新世(anthropocene)への地質学的変化(1950s〜)と、人間・機械・自然の3つのアクターの協働が求められる「Post-postmodern」(21C〜)への思想史上の転換が重なる現代に求められる視座について。
思考を変えるときは、time-perspective 時間軸を変えること。30年スパンだと企業の、100年スパンだと産業の、500年スパンだとメディアの盛衰が見えてくる。ここで一気にものさしを伸ばして、1万年スパンで、地球史上の位置付けから現代を考えてみようという初回講義。短期・超短期の時間軸に流されがちな忙しい日常、別のものさしで思考し語る時間・空間を持てる場。
人口増加、グローバリゼーション、テクノロジーの異常発展、核兵器etc.人間活動の爆発的増大による地球環境への影響が、小惑星の衝突や火山の大噴火といった大昔の自然現象に匹敵する影響を与えるようになったのが、(諸説あるが)1950年代。1万年以上続いた「完新世」が終わり、新たな地質年代区分のanthropocene(人新世)では、「地球と人類」の未来をワンセットで考えるフィロソフィーが求められる。
科学と技術で自然を支配しようと試み、神の死を宣言した近代、支配しようとしたはずの技術・自然が人間を破壊しうるというしっぺ返しの経験、科学主義批判と、宗教・スピリチュアリズム等の非合理的なもの復活etc. 多様性と複雑性のポストモダンから、Post-postmodernへ。
もはや「人間中心主義」では立ち行かないのがPost-postmodern。中空構造をもちながら、人間・機械・自然の協働を模索するときがきている。生命倫理・技術倫理・環境倫理の3つの倫理を横断する、「あいだ」の知の担い手(インターミディエイター)が必要。
現代のビジネスも、Post-postmodernを前提に、人間・機械・自然の3つのアクターの調和、協働を目指すものでなければならない。コンセプト(ESG投資やSDGs、寄付経済圏etc.)を打ち出しつつ、それを可能にする制度デザインや法整備を進めること、その両方が必要。これまでのマーケティングパラダイムを踏まえながら「生命論マーケティング」へ。これが次回以降のテーマ。
どうしても仕事を休めない人向け、メンタルいわしたときの「いのちだいじに」初動対応
私も昨年経験したので、近い世代の働きマンたちやそのパートナーからちょくちょく相談受けるのですが、メンタルいわしたときって初動対応がすごく大事で、そこでやれる限りの対応をがっとやれると、それだけ予後がよくなると思うので、参考にしてもらえればと思ってつらつらと書く。
僕は医師ではないので、あくまで経験者は語る的な位置づけでほどよく参考にしてもらえれば嬉しいです。
まず大前提として…
がっつり休職出来る人は休んだ方がぜっっったいに回復早いから、休めるなら休んでくれよな!頼むから!
ということを声を大にして伝えておきます。
ここでは、それでも、さまざまな、実にさまざまな事情があって、「そうは言っても仕事やすめねーんだよ今」って人を対象に(いや休んでほしいんだけども)、働きながらでもどうにかこうにか死なないためのアドバイス的な位置づけになります。
考え方: 作戦名「いのちだいじに」への切り替えを、自分と他人両方に、なるべく早く周知徹底する
ドラクエの作戦あるじゃないですか、「ガンガンいこうぜ」とか「じゅもんつかうな」とか。あれです。一刻もはやく「いのちだいじに」に切り替えてくれ。それを自分だけでなく周囲にも認知徹底してくれ。
多忙な働きマンがメンタルいわしたとき、自分も周囲も従来の「ガンガンいこうぜ」感覚のままでいると、絶対にギアが合わないのです。
だって!エネルギーの総量が!超下がってるから!瀕死だから!
切り替えるための方法はいくつかあるので、実行可能なやつは全部やるって感じで低温運用に切り替えてください。
“・通院する
・可能な範囲で周囲に自己開示・相談
・急ぎでない予定は全キャンセル
・新規の予定入れない
・渡せるタスク渡す
・それでも残るタスクだけに絞ってやる
・食事・睡眠絶対死守(運動は元気になってから)”
①まずは通院してくれ、話はそれからだ
会社や自宅からアクセス良い、最寄りの心療内科を今すぐ予約するんだ。最近は、仕事帰りの勤め人のために、夜やってるクリニックもあるぞ。僕も初診は夜遅くまで働いてクタクタになったその足で向かったぞ。
なんせ、メンタルいわしてるときって認知のゆがみんが現れて、正常な自己判断できない状態なってますんで、「まだ大丈夫」とか思ってるのだいたい大丈夫じゃないですから。はやめに医師に診てもらって、お薬出してもらうなり、会社に見せる用の診断書書いてもらうなりしてください。
そして定期通院のリズムをつくってください。相談相手が外部にいる、それだけで少し心が楽になります。
②可能な範囲で症状の自己開示と周囲への相談を
直接の上長、家族やパートナー、同僚や後輩など、日常生活や仕事でかかわる人たちに対して、可能な範囲で自己開示と、対処方針の相談をする。無理に一人で抱え込むよりは、"具体的"に開示・相談した時方が全体最適になりやすいと思います。
「今こういう状態で、こういうことはできるけど、こういうことはしんどいんだ」と、仕事や家庭運営上、"必要な範囲での弱さの共有"をする、ぐらいの感覚で良いと思います。
③世界は意外と回るので、急ぎでない予定は全キャンセル
上長などと相談してもらえればと思いますが、自分が抱えていた仕事のうち、どうしても今日・明日とか今週中とかでやらなきゃいけないことは、ほんとにマクロかつドライにみると案外少なかったりします。
「出来ないより出来るに越したことないけど、まぁしばらくペンディングしててもどうとでもなるな」みたいなプロジェクトとかタスクとか、割とあるんで、そのへんは上長と相談しながら、これを機に思い切って業務整理・優先順位判断してみてはどうでしょうか。
④新規の予定入れない
これはもう読んで字のごとくです。コントロール可能な範囲では、少なくとも短期的に急ぎの「新規案件」を入れる必然性ないのでバッサリ切りましょう。
それ以外でも、メンタル病む人に限って「業務外の業務」的な、諸方面からのふわっとした相談とかランチMTGとか入れられがちだったりします。そういうのぜんぶバッサーっとブロックしてくださいね。
⑤渡せるタスクはじゃんじゃか渡す
これを機に後輩たちに責任&役割を移譲しましょう。不安なら、判断軸だけしっかり抑えたりすり合わせの時間をつくった方が良いですが、仕事を任せて部下が育つってことは往々にしてあるので、良い機会だと思ってください。
⑥それでも残るタスクだけに絞って一撃必殺で仕事乗り切ろう
もうね、あとは、それでも渡せない、休めないなって案件だけに専念してください。大事な商談とかプレゼンとか。ほかの仕事ゼロにするぐらいの勢いで渡して、それでも休めないなって仕事だけ手元に残しましょう。
⑦食事・睡眠絶対死守(運動はもうちょい元気になってからじわじわと)
当たり前のことですが、食事・睡眠時間絶対死守です。しっかり寝るんだーーーー!
---------------------------------------------------------------------------
なんだか取り留めもなく書きましたが、とにかくですね、みなさん「いのちだいじに」どうにか生き延びてほしいわけです。
幸あれ
執筆日誌 2019/07/22
一日のこと
・就労移行支援事業所からのインターン生の受け入れ(1週間)
・元同僚が、3ヶ月の息子さんを連れてきてくれたのでみんなでランチ
・来客、MTGなど3つ4つ立て続けに
・ムスメのお迎え担当。鼻水・くしゃみが続いているので、その足で年のため小児科へ連れて行く。熱はないが一応お薬を。
・寝かしつけたまま、起き上がれず入眠
・早朝に、納期が近い研修資料をつくる
メモ
「弱さ」を開くことによる物語の共有化、認識の変化、支え合い、回復etc.といったよき方向に流れが生まれると良いが、そうもうまくいかないことも当然ある。理念や要素といったものはべてるの家をはじめ、先輩たちが示しているけれど。
ひとつ、本の中で触れなければいけない、再現性のある体験、エピソードを思い起こす。弱さがナイフに変わると言ったら良いのだろうか、というより、強さの鎧を脱げないことによる傷つけ合い。「強く生きてきた」年長の女性に、期待をかけられ、そして呆れられ、断絶する、という経験が数度ある。もっと前に差別が強い時代に苦労して勝ち取った方々。ガラスの天井もないのに、(そして彼女たちからしたら能力や機会があるように見えるのに)なよっとふにゃっとしていた僕。
生きてきた歴史と痛みに経緯を払いつつも、また別の人生を生きている者として、どういう態度で、どういう言葉をかわせばよかったのか、と振り返ることがある。次の断片では、そろそろ書ける、書かなきゃいけない気がする。昨年から話題になり、私も読んだ『キム・ジヨン』に連なるテーマだと思う。
船後さん、木村さんの当選にあたって、たまに目にする、「無責任じゃないのか」というこえ。本人のためをという体裁をとりながらの「よき優生思想」という感じがする。そして、本人がどういう意思で、なぜ今回の意思決定と行動に至ったかを、書かれたテキストを参照したり、本人の言葉を聞いたりした人は、無責任じゃないかと言う人たちのなかにはほとんどいないのではないかという予想がある。
アシスタント/パートナーとして名乗りを上げてくれた人に、お仕事の整理と連絡とご相談がまだできておらず、急ぎたい。
参考文献メモと過去記事整理も急ぎたい。
色々と、単発なんだけどちょっと重ためのお仕事が行列をなしている。一個一個やっていきつつ、執筆時間を捻出する。
読書の時間は少しずつ戻せてきている。
-----------------
執筆日誌 2019/07/21
一日のこと
・朝、仮面ライダージオウを見てから選挙に行く
・上野に移動、漆とロックの貝沼さんと今後の展開についてランチMTG
・川崎に移動、OPEN LABゲスト講師の石井政之さん出演の「ウェルトーーク」に参加@シェアハウスMAZARIBA
・帰宅、掃除したりムスメと遊んだりご飯食べたりお風呂入ったり
・全く進捗のなかった金土の執筆日誌を公開してから、途中で起きたムスメを寝かしつけたり選挙速報を見たりなんだりしているうちに自分も寝る。
メモ
先週の三連休もほとんど寝ていたが、この土日もそうだ。平日はかなりエネルギー戻ってきたなという感覚。行き帰り2駅ずつ歩くという日常の運動も再開。体力戻していかねば。
事務作業の負荷はだいぶ減ってきたのだが、短期的にゴリっと自分でやんなきゃいけない企画・構成・執筆系のしごとがタイミング重なると、ちょっとストレスがある。新規をなるべく請けないようにしているものの。
根本的に読書・執筆時間をブロックして、そこは死守するというモードの徹底が必要。
「雑」あるいは「雑然」というのが最近のキーワードのひとつ。関与の仕方に幅をもたせること。変わりゆくことを前提として、決めすぎないこと。
良くも悪くも日本に生きる人たちの多くが「元号」という物語構造の中に生きているということを実感。吉本まわりの騒動、選挙結果等に対する語り方として、平成・昭和の膿を出し切る、とか令和になって変わるだろうとか、そういうことが言われる。元号なんてグローバルにはなんの意味もないとか、西暦統一でいいやんとか、そういう逆向きの声も当然ある。利便性の意味では僕もけっこう同感するし、普段あまり元号を意識して生きていない。一方で、少なからぬ人たちがそれを意識し、発言し、行動する、ということで生まれるムードというものは確かにあると認めたほうが良い。結論としては、変わるものは変わるし、変わらないものは変わらないのだろうし、いつだって自分が変えたいと思うものを変えるための行動を重ねるだけなのだが、BGMや風向きの変化というものは起こるだろう。
執筆日誌 2019/07/19-20
毎日ちょっとずつでも「原稿」を書くぞ宣言をしたのに早くも落としている。安藤さんごめんなさい。
もうほんとにさすがに反省するぐらい飲んで酔っ払った金曜日の夜と、そのまま二日酔いでろくに機能しなかった土曜日です。そしてそれを書いているの今はもう日曜日の夜です。日曜日はまだ終わってない。ので、金・土曜日分だけ、執筆的にはなんの進捗もない日記を残す。懺悔。
一日のこと
金曜日
・朝、講演仕事のスライドをつくる
・翌週から職場での実習生受け入れの打ち合わせ(オンライン)
・講演対談相手とランチMTG
・某社にて企業で働く方向けの発達障害まわりの講演
・会社に戻って打ち合わせ2件
・その足で飲みに行く
・しこたま飲んで酔っ払って帰宅
土曜日
・午前、二日酔いでろくに機能しない
・友人たちとのBBQにツマ・ムスメと一緒に参加
・ツマが大学の用事。ムスメとご飯・お風呂→寝かしつけ
メモ
インタビュー原稿、ご本人確認お戻しあり、来週公開予定。嬉しい言葉をいただいた。大変長らくお待たせしました。
原稿が1つ終わっても第2, 第3の原稿が待っているのだ。
過去記事リストと参考文献リストの作成を急ぎたい。並べながら浮かんできたメモを書き留めつつ、今回の企画との関連付けをしていく作業が必要。
酒は飲んでも飲まれるな。反省。
「弱さ」をめぐる旅のはじまり
「適応障害ですかね。」
「そう思います。」
平日の夜、職場から徒歩5分のクリニックで、最近知り合った医師の先生とそう話したのは、今の会社で働きだして5年目の夏のことだった。
「仕事も人も、好きなんですよね。嫌な理由ないんですけど。でもしんどいんですよね。」
風邪をひいているわけでもないのにやたらと咳が出る。オフィスに向かうだけでドッと疲れる。ミーティング前には動悸がする。言葉以上に身体は正直だ。
適応障害というのは、特定のストレス要因に反応して心身の症状が起こる疾患である。受診の場に至ってなお「別に仕事が嫌なわけじゃなくて」と防衛線を張る僕に対して、「あなた、そろそろ限界ですよー」と身体が言っているのだ。
「俺もついにビョーキになったか」という、不思議な安堵と納得。「明日はどういう報告と相談をしようか」という、極めて実務的な対応方針の思案。そういう色々が混ぜこぜに頭を巡りつつも、先生に診断書を出してもらい、処方された抗うつ薬を帰り道の薬局で受け取った。
診断を受けた翌朝、通常通り出社し、パソコンを開いて、上長と人事部長にメールで報告した。直近で入っていた会議はキャンセルし、その他、急ぎでないもの、自分の手元でしばらく寝かせても当座支障がないものなど、いくつかの観点で業務を取捨選択し、緊急避難として減らせる限りの業務負荷とストレッサー回避をした。自分が診断を受けたこと、仕事についてはこんな対応をしていること、直近エネルギーが落ち込んでいて心配をかけるかもしれないが、自分を守りながら回復に向けてやれることをやっていこうと思っていること、などを妻に話した。それから翌週またクリニックに足を運び、職場との相談・対応状況を相談しつつ、業務調整をしながら療養を続けましょうという方針について話した。
家に帰る前にオフィス近くのベンチでパソコンを開き、その場でテキストを打つ。自分が現在「弱っている」ということ、一応のお墨付きとして、医師の診断を受けたこと、会社にも妻にも共有しつつ、業務調整をしながらもひとまずは仕事を続けてもいること、弱った自分のことを自分自身がどう捉えているか、等々を、なるべく淡々と、ジャッジを交えずに、かつ率直に現在地点の記録として書き残した。そしてその記事をSNSに放流した。
ほどなくして、SNSのコメント欄やメッセージボックスにたくさんの声が届いた。僕の心身の状況を気遣い、また支えようとしてくれるようなメッセージももちろん嬉しかったが、少し驚いたのは、それ以上に前のめりな様子で、さまざまな自己開示が寄せられてきたことだ。
「久しぶり。実は俺もいま同じような状態で」
「今、わたしのパートナーが心配なんだけど、どうしたらいいかわからなくて」
「数年前にまったく同じような状態だった。でも当時、そんなふうに職場や周囲に話すなんてできなかった。勇気あるよ」
などなど。
卒業して以来7,8年と会っていない、大学の同級生。
誰からも信頼されていていつも輝いていた先輩。
共通の友人の集まりで1,2度会って、SNSでゆるくつながっていたぐらいの知人。
採用の仕事で一度会ったぐらいの、当時学生だった子。
少し前に会社を辞めた元同僚。
それは「相談」というものではなかった。きっと「ただ、知らせたかった」のだと思う。そして僕に連絡をくれた。僕も、彼らのこえを受け取った。
お互いに何か即効性のある良い解決策を出せるはずもないし、「支え合う」というには滑稽なぐらい、お互いへろへろに弱っている同士のやり取りだ。だけど不思議と、気持ちが楽になった。具体的に何かをしてもらったわけではないが、診断を受けた直後に、自分と同じような経験をしてきた友人たちが幾人いる、という事実が、僕の心の引き出しの中にアーカイブされた。
「弱さ」を開示すると、似たような「弱さ」が引き寄せられて集まってくる。
巷のメンタルヘルスや生き辛さをめぐる言説では、「共依存」はよくないと、SNSは傷の舐め合いになりやすいと、そういうことがよく言われてきた。
ところが今回は不思議と、共倒れにはならなかった。むしろ、「弱さ」を開示しながら、一定の距離を保ち、弱いままでもつながっている、生きているという事実に、かすかに、しかし確かに支えられながら、それぞれがそれぞれに回復の道を歩んでいく。そんな感覚だったように思う。これはいったい、どういうことだろうか。
「強くある」ためのノウハウは見聞きするに事欠かない。企業研修で、ビジネス書で、ネットの記事で、「強くあれ」というメッセージが繰り返し発信されている。だけど、「弱った」状態でどう生きていくか、弱いままでも生きていける知恵については、教わったことがなかったように思う。
「弱さ」を開くことの可能性。人間関係の網の目の中で与え合うということ。自分の生を肯定する物語が開かれること。「弱さ」を携えて生きていく人たちと著者の対話を通して探求していきたい。
----
「弱さ」を巡る旅をしながら綴る一冊の書籍ができあがるまで、晶文社の安藤聡さんとの二人三脚で、また読者や友人たちとの対話のなかで、執筆プロセスを公開しながら進めていきます。
最初から構成を決めて埋めていくというより、旅をして、断片を書き連ねて、何を書くべきかがだんたんと見えてくる、そんな書籍になりそうです。
せっかくなら消費されない受発注を。パラレルワーカーにとって理想的なアシスタント/パートナーをどう考えるか
アシスタントを募集しようかな、と思っている。
ということを、何度かつぶやいてはいるものの、それは「アシスタント」という呼び方が適切なお仕事なのかどうか、またそれが1人なのか、複数なのか、どういう依頼の仕方が良いか、などなどを考えたままぷかぷか浮かしているのが現状である。
このnoteは思考の整理も兼ねたアレです。あわよくばの求人的なアレになるかもしれないけどならないかもしれないアレです(こんな書きぶりで手を上げてくれる人がいればとても嬉しいね)。
僕の仕事が一定の枠組みとリズムで安定しており、「アシスタント」と呼ばれる人に求める業務や待遇が明確であればよいのだけど(たとえば、基本的に漫画一本でやっていってるプロの漫画家さんで、抱えている週間連載を2本回すのにこういうスキルレベルの「アシスタント」が常時何人必要です、みたいな感じ)、いかんせん僕は、業種不定所在不定の浮浪者スタイルで働いているもので、継続反復的に発生する業務も散発的に発生する業務もあり、それをどのタイミングでどういう人に渡していけばみんなハッピーなのか、というのがなかなか難しいのである。
勤務先を含めて複数企業・複数プロジェクトにかかわっていて、溢れたタスクを各社のチーム内で吸収してもらうか、僕が自分の可処分所得の中で更に外部に委託していくか的なラインの判断の難しさ、である(ゆくゆくは、個人プロダクションの延長で、スタジオ的な存在を法人化していったほうが良いのかとか、まぁなんかそういう先々のことも念頭に置きつつ、思案)。
これはつまり、パラレルワーカーにとって理想的な業務アシスタント/パートナーとはどんな人か、あるいはどんな風に業務分解して複数人にお願いするのが良いのか、ということなのかもしれない。そういう問いに換言すれば、僕と同じような悩みを抱えている人は他にもいるように思う。
なので、基本的にはごくごく個人的な思考の整理ノートなのだが、読んでくれた物好きなみなさんにも参考になる一定の普遍性を意識しながら、書く。でもまぁ、僕の仕事に興味がない人は次の章だけ読めば良いと思う。
受発注をどう考えるか。短期的な効率性と、中長期的な持続発展性
まず、受注・発注関係における僕の考え方を棚卸ししておきたい。比較優位の原則、育成・習熟・関係構築による持続発展性、雇用創出、いかしあうつながりetc.がキーワードとなろうか。
結論から言うと、僕が色々やってるお仕事の一部を、「特定多数」の人に、なるべく「継続的に」、「入れ替え可能性」はちょろっと担保しながらお願いして、仕事創出やキャリア開発の機会に出来ると良いなと思っている。僕も助かるし、その人にとっても良い機会となる、という案件・関係がほとんどである、という状態をつくりたい。
各社・各プロジェクトごとの個別最適で考えると、現時点でその業務を依頼できる人のなかから、「より安く・より早く・より品質良く」できる人に発注するのが一番良い、となる。もちろん、この3つは基本的に同時成立し得ないトリレンマであるので、予算や納期とも相談しながら優先順位付けして、「今回は(も)この人に」と、発注の意思決定をするのが通常である。
企業A内のプロジェクトXに一定期間携わる中で発生するタスクは大きく
1)自分がやるべきやつ
2)チーム内の他のメンバーがやるべきやつ
3)自分やチームメンバーでも出来るし、短期的には中にいる自分たちでやったほうが早いけど、数が積み上がってくると大変だし、他の人にお願いできると助かるなー、というやつ
4)最初から外部への発注想定で走らせるやつ
に分けることができる。
もちろん、この1)〜4)の区分けも、ある時点を切り取ったときのものでしかなく、時間の流れの中では流動的である。4)の仕事を依頼していた人たちのうち、○○さんは一番筋が良いし、波長も合うし、他の業務もできそうだし、と社員として採用することもある。2)で活躍していたメンバーが独立したけど、業務委託で引き続きお願いする仕事が一部残る、ということもある。パラレルワークを前提とすると、そういうことが常時各地で起きるということだし、実際に起きている。
ただ、取り急ぎ「受発注関係の最適化」を考えるにあたって、一番悩ましいのは3)に該当するタスクだろう。業務への慣れや習熟だったり、人間関係の近さだったり、社内イントラへのアクセスだったりが参入障壁になって、「いろいろ書類取り交わして外注できるようにするのめんどくさいし、もう俺がやったほうが早いわー」という感じの業務。一個一個の難易度も工数も大したことないけど、放置しているとボディブローみたいに工数を圧迫する系のものだ。
特に、僕を含めパラレルワーカー的に働く人は、複数企業・複数プロジェクトとの関係の中で、ポロポロこぼれている3)的タスクをちょっとずつ地味に善意で拾ったりしていると、「あれー?思ったより自分の時間がないぞー」的状況に陥りやすいと思う。困ったな。
どんなオペレーションも、マニュアル化・仕組み化・自動化を進めることで一定属人性を低減させ、人を選ばず依頼しやすくはなるが、それでも、そのオペレーションを回すこと自体の習熟度の差や、周辺業務との連携やイレギュラー時の報・連・相をスムーズに進めやすい人間関係の構築など、属人性はゼロにならない。
ゆえに、同じタイプの仕事を同じ人が継続的にやった方がお互い効率的だよねという当たり前の現象は、雇用であれ業務委託であれ、本業であれ副業であれ一定発生する。一定規模のある企業体であれば、専門分化した部署をつくり、そこに人を採用し、育成していけば良い。企業や事業が存続し、成長を続けている限りはその分業体制を維持できる。
一方、お互いの自由意思に基づくゆるやかな連携・分業を建前/前提としたギルド的、パラレル的な働き方のネットワークではどうか。どんなふうに業務を融通しあい、個々人に一定のスキル習熟が果たされつつ、いざというときに自由に着脱可能な余白ー入れ替え可能性を残した状態でバランスするのか。メンバーシップ型の企業体よりは難しいパズルだと思う。
少なくとも、「とにかく安いとこに外注すりゃええねん」みたいな発想には立ちたくない。そういう買いたたきを繰り返していると、業界が、経済圏全体がやせ細っていって、いつか自分たちの首を締めることになると考える。
自分が携わる仕事の過程では、かかわる人たちに(お金の適正さはもちろんのこと)スキルや経験、ネットワーク等の資産が積み上がるようなやり方をしたい。消費する/されるのではない健やかな受発注の循環をデザインしたい。なるべくは。
こんなことをいつもぼやぼや考えているから、「時給xxxx円で、週○時間でアシスタントを1人、募集しまーす!」みたいな明快な求人をいつまでも出せない。困ったな。
フォーカスすべきことにフォーカスするために
書いている当の本人はどんなふうに働いているか。企業での社員として雇用、その他複数企業・NPOに業務委託でかかわり、それらの案件以外でも個人プロジェクトとして執筆活動、というパラレルワーカー。
それぞれ異なりながらも近しい領域であるので、自分の持っているスキルや、人的ネットワークが掛け算で良い作用に働きやすく、また時間と場所もかなり自由がきく立場でやらせてもらっている方だ。
企画・対話・問い立て・執筆・言語化を強みとして領域・職能のあいだをつなぐような役回り。
処理速度は早いほうだが、興味のないことは極端に腰が重くなる。好きな仕事であっても、完璧主義気味なところがこだわり・溜め込みグセとなり、まあまあに遅筆である。ギリギリにガッと企画書とか講演資料つくるみたいな、いつもお手玉してる感じ。
自由に自分で決められるとはいえ、当然ながらそれぞれのお仕事で決めた目標や役割や納期はあるので、常に複数ラインがダーッと走っているわけで、繁忙が重なって、ガッとつくらなきゃいけない重ためのタスクが列をなすことがしばしば。そういうときに細かいタスクがあると、思考と作業の邪魔をするので、そういうのをあまり溜め込まないためにも、そろそろアシスタント的な人と一緒に働いたほうが良いのではないかと感じている。一個一個は小さいのだけど、重なると時間を取られる、という類のものをもう少しなんとかできないかと思う。
全体通して見ても、本当はもう少し早期からまるっと渡せたであろうタスクとか、請けないほうが良かったかもしれないものもあり、そのあたりの見極め、脳みそのメモリの有効活用を、自分ひとりではなく、パートナーとして支えてくれる人がいると助かる。
もっと自分のやるべきことにフォーカスしたいし、そのために可能な限りそれ以外のものを渡していきたいという感覚が強くなっているし、怠惰な自分がフォーカスすべきことにフォーカスするためのケツたたきも含めて、環境調整が必要だと思う。
渡せるものをほぼ全部渡せたとしたら、僕の手元には定常・定型の事務作業はほとんどゼロになるはずだ。じゃあ何にフォーカスすべきかというと、非定形・非線形の企画・執筆・制作活動となるのだが、それとセット、平時からの豊富なインプットを可能にする「ヒマ」を持て余すことが許されなければならない。
ときにはテーマと狙いをもって、時にはランダムに、読書・調べ物・旅・インタビューetc.のインプットをして、それらが、コンテンツとして単発のアウトプットに使われることもあれば、継続的なプロジェクトの中で、研究・執筆・企画・出版etc.の素材となることもある。傍から見ると遊んでるっぽく見えるかもしれないが、それが創作のための余白なのだと割り切って、それ以外の真面目な仕事っぽく見える作業を、全部思い切って堂々と他の人に渡していく、という勇気を出す時期なのだと思う。まぁそれが他者から見てもわかりやすいようにする必要はあるが。
短期的には、主宰しているOPEN LABと、なかなか進んでいないけどちゃんと進めねばならない単著出版の企画が、かなりの度合いインプット勝負かつ、マイプロジェクトとしても代表作になり得るので、これを形にすることが第一。並行して、ちょっとずつ、個人サイトのリニューアルも準備中。noteやSNSだとなかなか伝わりにくい、仕事の全体像と、日常的なインプット・アウトプットサイクルのための場、思想の苗床として、そこに集約していく。
中長期的には、日常的なインプットとアウトプットが、その都度なんらかのプロジェクト&パブリッシングに繋がる体制が作れると良いのだと思う。アシスタント、ないしパートナー的に必要としているのはコーディネーターと編集者。そして、さまざまな分野での表現者・研究者とのネットワークだ。
どんな人とチームを組みたいか
具体的にはどんな業務が想定されるか どういう人なら合いそうか。
①コーディネーター:
各方面との事務手続きやコミュニケーションを滞りなく、僕の手元作業を極小化しつつ進めてくれるような人。
メール、イベント告知、企画書etc.各種テキストドキュメントのたたき作成、一部はアシスタントとしてそのまま直接対応・処理したり、スケジュール管理、請求書、領収書、宿泊予約や精算、イベントやプロジェクトで誰かとさらに連携する際の業務依頼…などなど。あとは音源の文字起こしもちょくちょく(これは単発で切り出しやすいが)
まずは案件単価でいくつかお願いしつつ、慣れてきたら僕の日常的な動きや各種アカウントとの連携度合いを高めてもろもろ柔軟に拾ってもらいながら時給でのお仕事に切り替えていくのが良いか、というイメージ。
大前提、そういう事務局的動きが好きだったり苦にならない人。加えて、僕が仕事をしている領域への関心が高かったり、事務処理をする過程での僕や関係者とのコミュニケーションを通して自然とインプットをしていけるような人だと良いと思う。
時間には比較的融通が効くとが、オンライン・チャットコミュニケーションがなるべくスムーズな方が良い。
リモート可能。上記の前提条件が先にはなるが、せっかくなら、家庭や心身の事情で、外出してのオフィスワークが難しい方のお仕事にしていけると良いなと思っている。
②編集者:
個人付きの担当編集者的な人。
日頃のインプットを踏まえての、各種チャネルでの発信やコンテンツの提案、対話、その他いろいろ雑談刺激。やると決まったことのケツたたき、個人サイトやSNSなど、ゆるゆるやっているものをwebマーケ的にかわりに数字追っていったり、過去記事等の運用をしたり、そもそも個人メディアをどうしていくかみたいなことを一緒に考えたり、みたいな。
自分がパラレルで関わっている企業やプロジェクト、それぞれにも編集者的な人はいるのだけど、そうではなくて、総体としての僕の仕事や個人メディアをどうやってつくり、育てていくかを一緒に考えてくれるような、そういう人と出会いたいと思う。
世代が近く、分野が違いながらも問題意識が合って、ディスカッションも楽しいなという知己は多いるのだが、それぞれにまぁ多忙である。優秀な編集者というのは、一箇所だけで囲い込むのは難しいし、そうでないほうが良いのではないかという話にもなる。
ただ、このさき、自分の本を出したり、プロジェクトが増えたりして、もう少し僕個人の仕事が立ってくれば、ライフキャリアにおけるそれなりの時間を僕と一緒に過ごして伴走してくれる人が現れるかもしれないし、そういう人を自信を持って、また適切な待遇で迎えられるようにしたいとは考えている(シニアな人と駆け出しアシスタント的にやりたい人と、複数人の組み合わせ分担でやったほうが個々人にとってちょうど良いご依頼ができるかもしれない)。
③表現者・研究者:
これは、本記事の「アシスタント」的な話からはそれるので短くするが、上記①②の人に助けてもらいながら、今後ますますパラレルに、色んなプロジェクトをやっていくぞ、となったときに、さまざまな分野での信頼できる表現者・研究者とのつながりが非常に大事になっていくと思う。一定の相互理解と信頼のもと、それぞれに仕事をしているんだけど、たまに一緒に作品制作やプロジェクト参画ができる、そういう仲間を増やしていきたい。
短期的には、①のコーディネーター的な人と、まずは1人2人、業務委託でお仕事をお願いして、余白時間を少しでもつくる。ほんで、いい加減にちゃんと執筆を進めて本を出したり個人サイトのリニューアルをしたりする。それをPRしつつ、先行投資で編集者を募集する、みたいなことを考えている。個人サイトに仕事のポートフォリオや日々の思索の足跡を集約して残しておき、有機的につながるべき人とつながっていけるような循環をつくりたい。
企業の社長ともなれば「意思決定が一番大事だから、それ以外はほとんど秘書や部下に任せる」とかできるし、したら良いのだと思う。僕はそこまで偉くないのと、意思決定に至る前後の道筋も含めて関わり方が多様なので、そのなかでの良いやり方を考えなければいけないと思う。自分という企業を経営すると考えたときに、何にフォーカスして、どういうリソース配分をするかという話でもあるので、本質は同じことなのかもしれない。みんなはどうだろう?
#30 「ツマと、KPT: 5月の家族会議」2019/06/いつやったっけ…?
KPT形式で一ヶ月を振り返る、スズキとヨシダの家族会議。
これを書いている時点でもう6月も下旬なわけですが、5月の振り返りを今更noteに上げたりします。
ツマ「なんかあれだよね、毎回Keepが一番出てこないよね」
オット「いやまぁ、これまで挙げてきたことはそれなりに継続できてるし良いってことなのでは」
ツマ「というかもう、日々満身創痍で考える余裕ないっていうね」
オット「めっちゃ疲れてますね。もうあれだ、みんながんばって生きてるからそれだけではなまる理論だ。今月のKは、『みんながんばって生きてる』」
ツマ「ゆうへいもわたしもいちかも『みんながんばって生きてる』」
オット「Problemは前月に引き続きなんだけど、本は増えるいっぽうで、もう引くほどひどい状態です。机が物置。床まで侵食してきた最近」
ツマ「いちかが近づきすぎないように、テレビを壁掛けにしようってのも、未達で5月が終わりまして」
オット「これはもう、アウトソーシングするしかないのでは。スーパーお助けフレンズを探そう」
ツマ「スーパーお助けフレンズ」
オット「なんかこう、片付けとか収納が趣味な人に、謝礼1万円+本棚とか必要経費実費みたいな感じで、もうまるっとレイアウト改善お任せしちゃいたい。こんまりみたいに本捨てない人ね」
ツマ「こんまりみたいに本捨てない人」
オット「とりあえずFacebookとTwitterで募集かけてみよう」
ツマ「あとなんか、KでもPでもないけど、トピック的なのあれば」
オット「それはあれよ、重大事件が。満を持して精神科にADHD診断取りにいったら、『いやあなたASDのほうが全然強いよー』って言われた事件。な、なんだってー!」
ツマ「それは重大トピックだね」
オット「こういうのはやっぱり自己判断せず専門家に見てもらうのが大事ということで。その場でパーソナリティ傾向も見てもらったし、これだけでまたnote一本書けるぐらいの出来事でしたよ」
ツマ「お、おう」
前回はこちら↓
「ツマと、」はこちら
世代の宿題、そしてわたしの宿題 ぶっちゃけキッツイなーと思うこともあるんですけども
世代の宿題、というのがあるよな。たくさんあるんだけど、その中で、自分の宿題、というのがあるよな。そう考えながら仕事をしている。
ほんの数年前までは自分が生きるのに必死だったけど、いや今も必死なんだけど、歳を取るにつれ、この宿題は自分たちが受け止めてどうにかせんといかんよなという感覚が強まってくる。
全体的にカネも時間もなくてみんな必死のヘロヘロだよというムードの中で、真綿で首を絞められるような構造の中で、1)もう一度、私たちが拠って立つ倫理を共有すること、2) 魂を売らずに自律・持続可能なメディア環境をつくること、3)個人の心身がボロボロにならないようなクッションを敷くこと、そういうことを考えている。
まとまってはいない。仕事帰りに疲れた脳みそで書く。すまん。
宿題その① もう一度、私たちが拠って立つ倫理を共有すること
相模原、の後の、登戸と、元次官の息子殺傷。最近、頭の片隅にずっとあって、自分の思考と行動と言葉に影響している。日に日にその残響は実感を増す。
僕の同世代は、だいたい大学卒業前後というタイミングで東日本大震災を目の当たりにした。個人もNPOもボランティア団体も企業派遣も、みんなそれぞれの関わり方で、現地に飛び込んだり後方支援したり…僕もその中にいた。もちろん課題はまだ全部片付いてはいないが、損得ではない何かに、多かれ少なかれ「突き動かされて」いたのだと思う。
その少し前から、SNSが勃興したり、greenz.jpとかソトコトとかオルタナとか、そういう「ソーシャル系」の先駆けとも言えるメディアが立ち上がったりして、まだまだマスには遠かったかもしれないけど、社会的なイシューにコミットすることを、一定カジュアルにしたり、かっこよくしたり、そういうことをちょっと上の先輩たちがやってきた。
障害者差別解消法が施行されたり、法定雇用率がアップしたり、あとはなんだ、働き方改革とか、ダイバーシティ&インクルージョンとか、SDGsとか、レインボーとか、心のバリアフリーとか、オリ・パラとか、とにかく少なくともお題目としては、色々、掲げられてきたはずだ。
そういう「前進してる感」が、まがりなりにもちょっとずつ積み重なってきたはずの機運が、1つ、2つ、3つと、片手で収まる数の事件で、オオカミの一息で吹き飛ばされた子豚の藁小屋よろしく、あっけなく崩れてしまった。そんな感覚に陥る。
やってる方はそれはそれで真剣に企画してきたはずなんだけど、それでも、ソーシャルなあれやこれやをオシャレにしていくあれやこれやが茶番みたいに思えてくる。くそう。
ちゃんと「怒る」、ちゃんと「それはダメだ」と言うことの必要性を感じる。一方で、敵を想定した短期的なキャンペーンでは、根本解決に至らないことも知っている。
彼らをして、その行動に至らしめた構造こそを問わねばならないことはわかっている。しかし、それにしても、余裕がない。社会に、私に。
障害のある人に限らず、誰もが「役に立たなければいけない」というプレッシャーにさいなまれているように見える。無意識に、しかし水が染み渡るかのように、優生主義や能力主義の亡霊が私たちの思考と行動に影響しているように思える。
彼らの行動選択自体にNOをちゃんと言わねばならないということと、社会全体の「余裕の無さ」を前にして、どう伝えれば届くのかということ。後者はより難しい宿題だ。
倫理を打ち立てなければならない。方法はまだ見えない。だけどそれが必要なのは確かだ。
誰かを悪者にして溜飲を下げるのではない、歴史と構造と倫理へのまなざしを持った、愛と知性が必要だ。
宿題その② 魂を売らずに自律・持続可能なメディア環境をつくること
先立つものはお金である。それも、紐付きでないお金だ。あるいは十分に分散されたポートフォリオだ。
今日こんな記事を読んだ。
書いていることはいちいち正論である。僕もこんないい子ぶったツイートをした。
しかし一方で、ぐぬぬ、である。
ここに書かれている「昔話」にあるような、「正直さ」と「めんどくささ」をもって、メディアと編集部が堂々とクライアントや広告部と渡り合える余裕をもった媒体が、今、日本のどこにあるのか。
高級ブランドと一流のクリエイターと、信頼関係を築くに至る、編集者の深い教養とセンスと、ネットワークと。それらを貯める余裕がほとんどの媒体の編集者には、いまない。
それで良いとも、余裕がないからしょうがないとも思っていないからこそ、歯がゆい。
「ウェブ以後」の、どんどんコンテンツが無料化されていく流れのなかで、人材育成のための時間と潤沢な制作費・育成費をどうやってつくるのか。魂を売らずに自律・継続可能なメディア環境をどうつくるのか。
「タイアップ記事なんて、なくなればいい」とまで勇ましいことを言い切れない現状に歯ぎしりしながら、次のメディア環境と経済圏をどうやってつくればいいねんって試行を、同世代の友人たちと、一緒に、あるいはそれぞれに、けっこう必死こいてやってる。だいぶ無理ゲーやなと思いつつ、活路を探している。
宿題その③ 個人の心身がボロボロにならないようなクッションを敷くこと
それでいて、自分も周囲の人も倒れないで済むように、ということ。
人口ボーナスに支えられた高度経済成長は今は昔。働けば働くほど豊かになる保障もなく、しかしぼんやりしていると食っていけない。いやーキッツい。しかしそれでも、いやだからこそ、心身の健康を守るということを大事にしないと、とても続けてられない。
昨年、体調を崩した。まだ治りきっちゃいない。それでもどうにか、こうにか、やっている。
5年ぶり、10年ぶりに、知人友人から連絡がくる。「実は僕も」「実はパートナーが」まじかお前もか。よく生きててくれた。しかし大変だよなお互い。と、戦地で同胞に会ったかのような気分である。病院やカウンセリングを紹介する。たまに飯でも食おうやと声をかける。あとは、祈る。そんな感じ。
心身をボロボロにするまで走ることはない。そんな無理を重ねて自己疎外をしていては宿題1も2も到底ムリなので。
疲れたら休む。困ったら助けを求める。自分がちょっと余裕があるときは、しんどくなっている人を支える。そういう循環をどうにかこうにか回していく。
粗にして多な、孤立しない繋がりを、クッションを、そこここに敷いていく。ひとつで全部を救おうとしない。非力さを認める。同時に、非力な支え合いの持つ力を、信じる。
そんなことを考えている。
すまん、俺も寝る。みんなも、休んでくれよな。
「こころの病」とのなが〜いお付き合い、あるいはサステナブルメンヘラのすすめ - 適応障害・抑うつを経験した私の場合
昨年の7月に適応障害と抑うつ症状との診断を受けた。もうすぐ1年が経つのか。
診断を受ける前は、オフィスに着くと動悸や咳や汗が出て、不安や焦燥感に襲われた。そういった「急性症状」は今は全くない。
適応障害は、原因となるストレスから距離をあけ、適切な休息・療養をすれば、通常半年ぐらいで回復すると言われている。
実際、良くなったと思う。
少し状況が変わって身軽になり、過度なプレッシャーやストレスを感じないで済むような働き方・就労環境をつくることができた。自分で時間・場所・内容の裁量をより効かせられるようになったのが大きく、本業・副業問わず、色々工夫しながらうまいこと続けられているとは思う。
だから今が「適応障害」かというと、その字面から受ける印象と、身体感覚にはややギャップがある。
しかしながら、今が「寛解」の絶好調かというと、そうとも言えない。
まず、体力は明確に落ちた。
以前より疲れやすくなっている。
平日、仕事に支障の出ないパフォーマンスを出せてはいるが、土日にはもう体力が残っていない。家事・育児の合間はほとんどボヘーっと寝ている。
ちょっと気が重たい案件があると、堪える。
常時ストレスにさらされているわけではないので、ちょっとヘビーな交渉だったり、人のケアに関することだったりが局所的に発生しても十分に対応可能なレベルなのだが、終わったあとの数日は、反動でどよーんとなる。
ストレスに対する「感度が上がった」、とみなすのか。
無理をして働いて麻痺していた感覚が「正常に戻った」、とみなすのか。
もともとのパーソナリティから来る社会適応上のストレスに対して、心と身体が「より素直に反応するようになった」、とみなすのか。
いずれが適切な表現なのか(あるいはこの全てか)わからないが、とにかくそんな感じであるので、「絶好調!」って感覚はしばらく来ていない。長時間ワークはもう無理で、瞬間最大風速でなんとかやっている感じ。
引き続き、寝る前に一錠の抗うつ薬と、月に一回の通院は継続している。
「お薬、いつ頃まで必要でしょうかね」という話を先生ともする。
「ゆうへいくん自身はどう思う?」と先生。
「うーん、体調とか、疲れやすさとか考えると、まだ回復しきったとは言えないな、もうちょい必要かなって感覚です」と僕。
「うん、そうだろうね」と先生。
自己認識は出来ているし、順調な方だよとも言われるし、そう思う。
(僕の場合は休職しないという選択肢をとったので、もっと早く回復したかもなというifはあるが、それも含めて自分で選んだし、その中でうまくやった方だと思う)
それでも、時おり考えてはちょっと、どよーんとする。
これはいつまで続くんだろう。
「寛解」とはいったい、なんだろう。と。
どよーん。
…と、書いてみるなどするが、とはいえ7-8割はもう「分かって」いて。
「すっかり元通りに元気に」なることをゴールとすると、きっとうまくいかない。
発症以後の、ちょっと疲れやすく繊細になった我が心身と、なが〜い目線でお付き合いしていくということなんだろうな、と思う。
*
自分もこんな体たらくだが、いや、だからこそなのか、20代の、自分より少し若い子たちの相談に乗ることが多い。「メンタルヘルス相談」と「キャリア相談」と「家族・パートナーシップ相談」とが、人によってそれぞれの成分でブレンドされたよもやま人生相談である。
セルフケアの力が弱かったり、それを高める経験が不足していたり、経験を積んでいくための伴走者とつながっていなかったり、という子が多いのが気になっている。
それまでの生育歴も関係して、本人の自己肯定感の低さ、見捨てられ不安などから、無理に「がんばろう」としてしまう。相談ができずに、溜め込んでしまう。
結果、ストレッサーから距離を開けるのが遅くなったり、受診に至るまで足踏みしたりする。
僕に話してくれた段階で、「いや、それは早く病院いこ?」って状態にある場合は、僕の主治医を含めた信頼できる&相談しやすいところを紹介して受診を促すなどしている。
急性期はとにかく医療とつながっての治療・休養が第一だと思うが、もう一つ気になるのは、休職明け等のセルフケアや生活・業務リズムづくりが難しく、頑張りすぎてまたダウンしてしまう、というケースが少なくないことだ。
私も人のこと言えないのだが、急性期を経たあとは、いかにセルフケアを丁寧にやっていくかが大事だとひしひし感じる。
ただ、メンタルいわしたあとは、心も身体も体力の上限値が減退しているので、ひとりでなんとかしようとするとだいたいうまくいかない。サステイナブルな生活リズムとセルフケア方法を確立するために、急性期を経た「その後」も相談できる相手と繋がり続けることが大切だ。
定期的な通院はもちろんだが、職場においても、上司や同僚との面談をこまめに入れて、相談しやすい時間や関係、あるいは周囲に気づいてもらいやすい機会を意図して組み込んでいくことが必要だと思う(休職前の感覚でタスク詰め込むと絶対詰むので…)。
結局のところ、
・十分な休息と睡眠
・バランスの取れた食事
・適度な運動
・家族や趣味の時間など、リラックスできる時間の確保
などなど…健康になるための「当たり前の要素」を、ないがしろにせず一個一個丁寧に満たしていくのが一番の安定の道なのだと思う。
31歳、そもそも体力が落ち始める年齢に差し掛かっていたという要素もあるだろうが、僕はもう、以前のように朝早くから夜遅くまで働き続けることはできない身体になった。
夜や土日に、はみ出たタスクを無理やり終わらせるという芸当ができなくなったわけだから、「アディショナルタイムは無い」という前提で仕事を組むしかないのである。
逆に、睡眠や食事、運動など、健康維持のために必要な時間は何があろうと最優先でブロックする、という前提で生活設計しないといけない(まだ完璧にはできていないけど)
「総量」が少なくなった稼働時間でどう稼いでいくか、ということが今後の職業生活で必須条件になってしまったようだけど、今の自分なら案外とやれそうな気もしているし、それはそれで試行錯誤を楽しんでいこうかな、と思う。
「その後の不自由」を生きるとは、きっとそういうことなのだろうし、「回復とは、回復し続けること」だと先輩たちも言っている。
Diary: 2019/05/28
「もうなんかやっぱり最終的にはフィクションいくしかないんだよね」
売文業をしている同世代の友人たち何人かと、それぞれ違うタイミングで同じような話になった。
本当に切実なことはフィクションを通してしか語りえないのではないかという感覚が強まる。
例の幻冬舎のニュースなどを見ていると、作品を作ることと、作り続けるための環境・基盤を整えていくことと両方やっていかないと、いつ足元が揺るがされるかわかったものじゃないなと思う。
どちらかが終わってからもう片方を、ということはありえず、どちらも「これで完成」ということはないのだから、両面展開でやっていくしかないのだろうけど、脳みその使い方が真逆なものだから、なかなかどうして難しい。
お金というのは、いつでも誰かの物で、それを受け取ることの意味合いや責任が違ってくるから、金額の多寡だけでなく、受け取り方や対価の提供方法、その頻度や分散なども含めて健やかなあり方を考えなければならない。
これは「生まれてしまった」私たちのための、祝福と再生の歌だ ZOC「family name」
「すごい社会包摂アイドル出てきた」
友人が教えてくれたリンクを何気なくクリックしたらガツンとやられた。
うわ、ちょっとこれ、すごいわ。
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IytBgF3UhP0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
ZOCは、藍染カレン、戦慄かなの、香椎かてぃ、西井万理那、兎凪さやか、そして「共犯者」大森靖子の6名からなるアイドルグループだ。
family name 同じ呪いで
だからって光を諦めないよ
彼女たちにとって、family name、つまり親の姓は、選ぶことができずに課せられた「呪い」である。
生まれる-be bornと受動態で表現されるように、子は生まれてくる家や親を選べない。
そして、生まれたばかりの子どもやまだ自活できない若者にとって、親は庇護者であると同時に権力者である。
「呪い」とまでは言わなくとも、生まれた家や親に対してアンビバレントな感情を抱えている、少なくとも抱えた経験のある人は少なくないだろう。
選ぶことのできない呪い、それでもわたしはわたしの人生に光あることを諦めない。「family name」は、”生まれてしまった”運命に悩み翻弄されるすべての人たちに向けた、祝福と再生の歌だ。
ZOCの公式サイト上ではメンバーそれぞれのプロフィール写真とともに、2-3行の簡潔な紹介文が添えられている。
「毎夜ぼっちで踊ってた熊本のワンルーム・ロンリーダンサー」「少年院帰り」「孤高の横須賀バカヤンキー」「完全セルフプロデュースアイドル」「女子百八のコンプレックス」…そんな言葉が並ぶ。
僕は彼女たちの詳しい生い立ちを知らないが、family nameを「呪い」と言い切ることに説得力を持たせる程度には、「何かあったんだろう」と部外者が想像するに難くない、(曲中でも自ら歌っているが)「治安悪い」顔ぶれである。
彼女たちが生きてきたこれまでの歴史それ自体が、きっとZOCというユニット、そして彼女たちが歌う「family name」に力強さをもたらしていることは間違いないと思う。
だけど、それ以上に僕がZOCに惹かれるのは、彼女たちが「かわいそうなマイノリティ」枠に決して回収されない、気高さと疾さと、危うさとしたたかさを携えた存在だからだ。
かわいそう抜きでもかわいいし
私をぎゅってしないなんておかしい
という歌詞は、上記のようなプロフィールを開示したアイドルに対して、今後当然に想定されるような有象無象のマウンティングーやたらと不幸な過去ばっかり聞きだして強調したがるインタビューとか、君たち大変だったんね守ってあげようと寄ってくるオッサンたちとかに対する牽制にもなっている。
かわいそうかどうかなんてどうだっていいから、今この場で歌って踊っている私たちを見ろ、そして祝福しろ。
そんな、「アイドル(偶像)」として立つことへの矜持が感じられる。
そして僕が一番好きなのはここ。
いらない感情しか売らないから
消費されたって消えはしない
最初に聴いたとき、これはものすごい人間讃歌だと思った。
消費上等、あんたたちが見てるものが<わたし>のすべてと思うなよ、と。
個人が、特に女性が「自分語り」をコンテンツにするたびに「切り売りだ」なんだと説教が湧いてくるのが昨今のインターネット言論空間だ(僕はそれをクソだなと思っている)が、書かずには、語らずにはいられない切実さをもって言葉を絞り出している人たちすべてにとっての福音であり包摂となる歌だと思う。
「孤独を孤立させない」
これがZOCのコンセプトだという。
人はどこまで行っても孤独だ。
彼女たち6人も、彼女たちの歌を聴く人たちも、これを書いている私も、これを読んでくれているあなたも、伝わらないもどかしさの中でこれまでもこれからもずーっと、孤独を生きていく。
それぞれがそれぞれに呪いを背負って生きていくなかで、孤立しないで共にあることは可能なのか。
彼女たちの答えは、ただただひたすらに「クッソ生きてやる」ことなのだろう。この世の果てまで。
曲の後半。夜の街を駆け抜け、出会う彼女たち。
そして最後に再び高らかに歌うのだ。
family name 同じ呪いで
だからって光を諦めないよ
朝焼けの河川敷で肩を組むその姿は、何よりも美しく、眩しい。