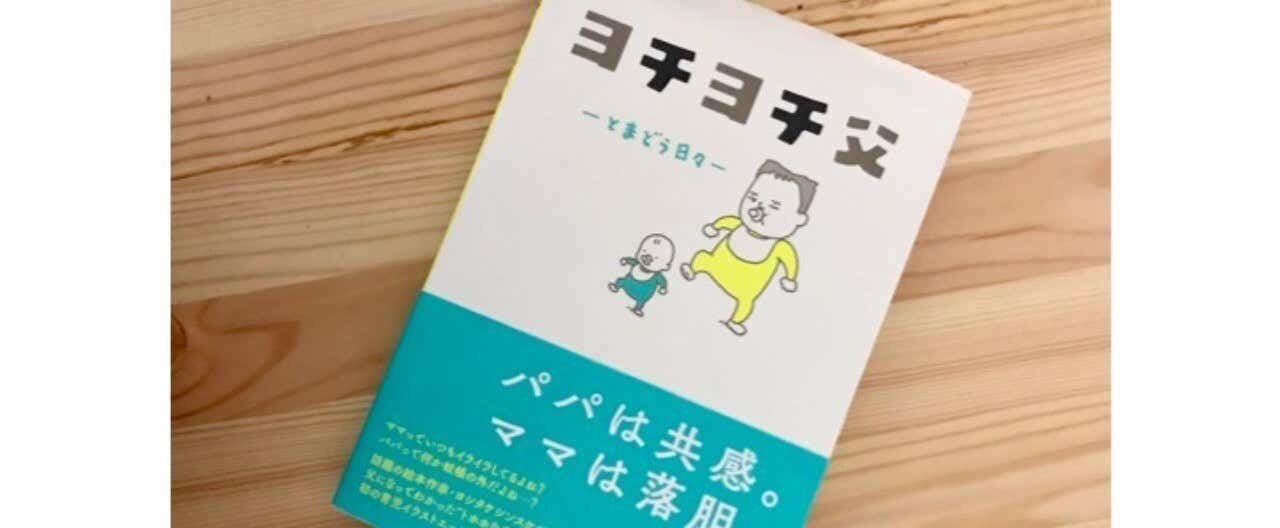「産休・育休のひとつひとつのタスク自体はたぶん大したことなくって。それよりも、コミュニケーションの相手がものすごく限定されるのが大きいんだということを、わかっておいてほしい」
産休に入り、高尾の実家に帰ったツマとの「産休はなれ暮らし」が始まって2週間。
子どもが産まれてからは否が応でも慌ただしい生活が始まるのだから、今のうちにお互いが大事にしたいこと、お互いに求めることを整理して言葉にしておこうという提案をツマからもらい、①人としての生活の自立、②ツマ/オットとしての生活、③家族の一員としての生活、④ママ/パパとしての生活の4つの軸で、今出来ているから維持してほしいこと、これから出来るようになってほしいこと・気をつけてほしいことをお互いに書き出して交換した。
その時のやり取りの中でツマから言われたのが冒頭の言葉。
言われてみれば確かにそうだな、という話なのだけど、改めてそれを要望としてまっすぐに伝えられるまで、ことの重大さは自覚し切っていなかったと思う。
ツマの実家ぐらしが始まってから、週に2回はあちらに顔を出すということをしているのだけど、やはり仕事の関係もあり、夜遅くに着いてメシ食って泊まって早朝また出社…みたいな感じになってしまって、わたし自身がツマの「昼間の生活」と交わることはない。
時々、「ヒマー」とLINEが飛んでくるが、日中なかなかタイムリーにお返事をできることもないのが正直なところ。しかし、「ヒマだ」というツマの言葉は、けっこう馬鹿にならないシグナルだったのだ。
ツマが産休に入るとか実家に帰るとかいうのを、「出産に備えた休み」などと素朴に考えていると見落とすのが、これまで会社で働き、都内でさまざまな人と関わっていたツマの「人間関係のチャネルが急に限定される」ということ。
身体のなかの赤子のためにも健康に気をつけながら、犬の散歩をして、買い物やごはんの支度をして、その合間に母親と分担しながら祖母の介護をし…といった生活範囲の中では、基本的にツマの話し相手は家族しかいない。
時折やって来る友人やオット(わたし)は、ツマと外界を結ぶ数少ない"窓口"なのだ。
一方でわたしは、社内外で毎日色んな人と仕事をしたり出会ったりして、その上にプラスオンでツマやツマの実家ご家族との接点がある。前提が真逆なのだ。うっかりするとそれを忘れてしまう。
わたしたち男性は、ともすれば量的・物理的ソリューションというか、「産前産後や育児のあれやこれやのタスクを自分がどれだけ担えるか、それはツマに比して不十分ではないか」みたいな観点で頑張ろうとしたりするんだが、実タスクを何%担っているかなどといった”担当業務”の問題よりも、ツマとの他愛のないコミュニケーションの時間をどれだけ持てているのか?という方がよっぽど大事なのかもしれない。
ツマが産休に入る前は、「週3で顔出すよ!」などと豪語していたのだが、やはりそれなりに移動距離はあり、体力的にも、仕事の時間的にも、週2回で精一杯というのが実態である。でも、「疲れるから」といってこのラインを下回るようなことは絶対にするまい…とは決めている。
そんなに毎日ドラマチックなことばかり起こるわけではありませぬが、限られた時間だからこそ、わたしはツマに毎回いろんなおみやげ話を持って帰れるぐらいには一生懸命に昼間を過ごそうと思うのだ。