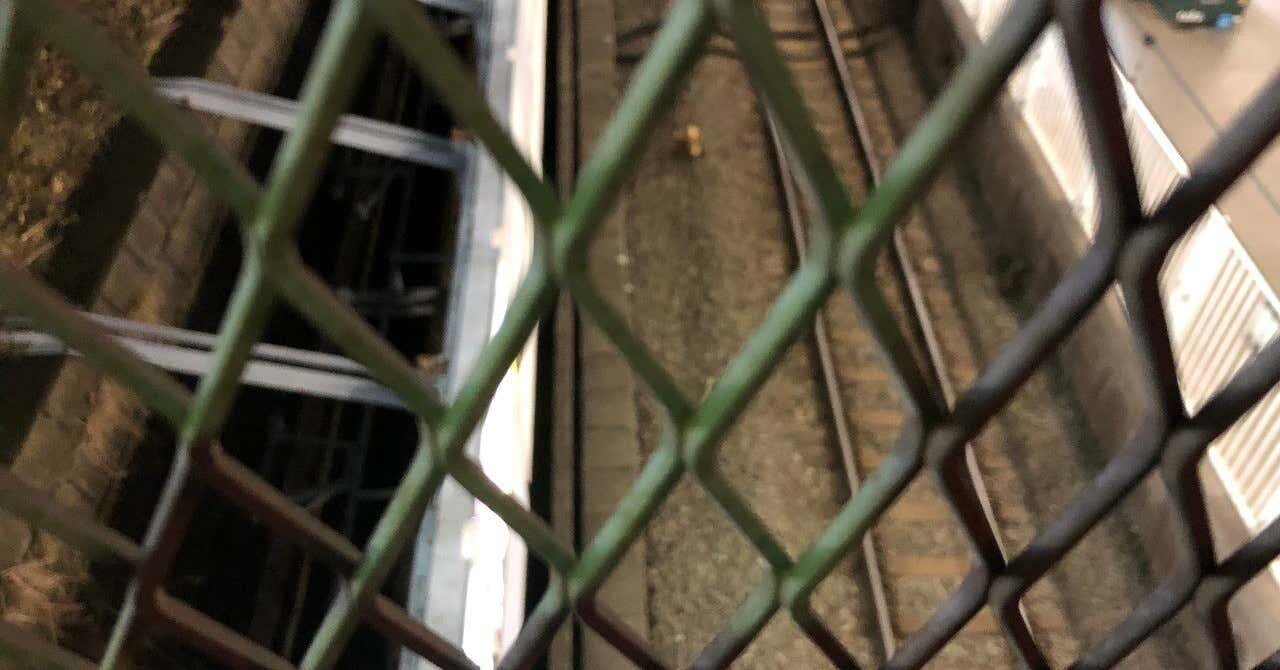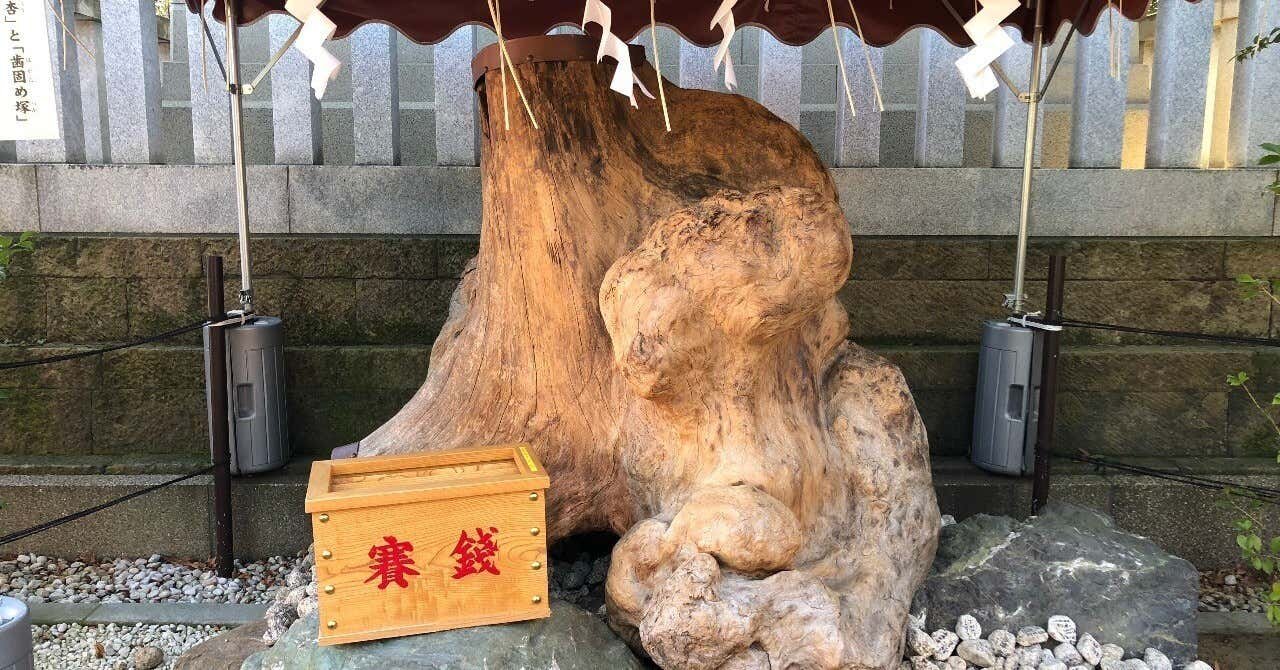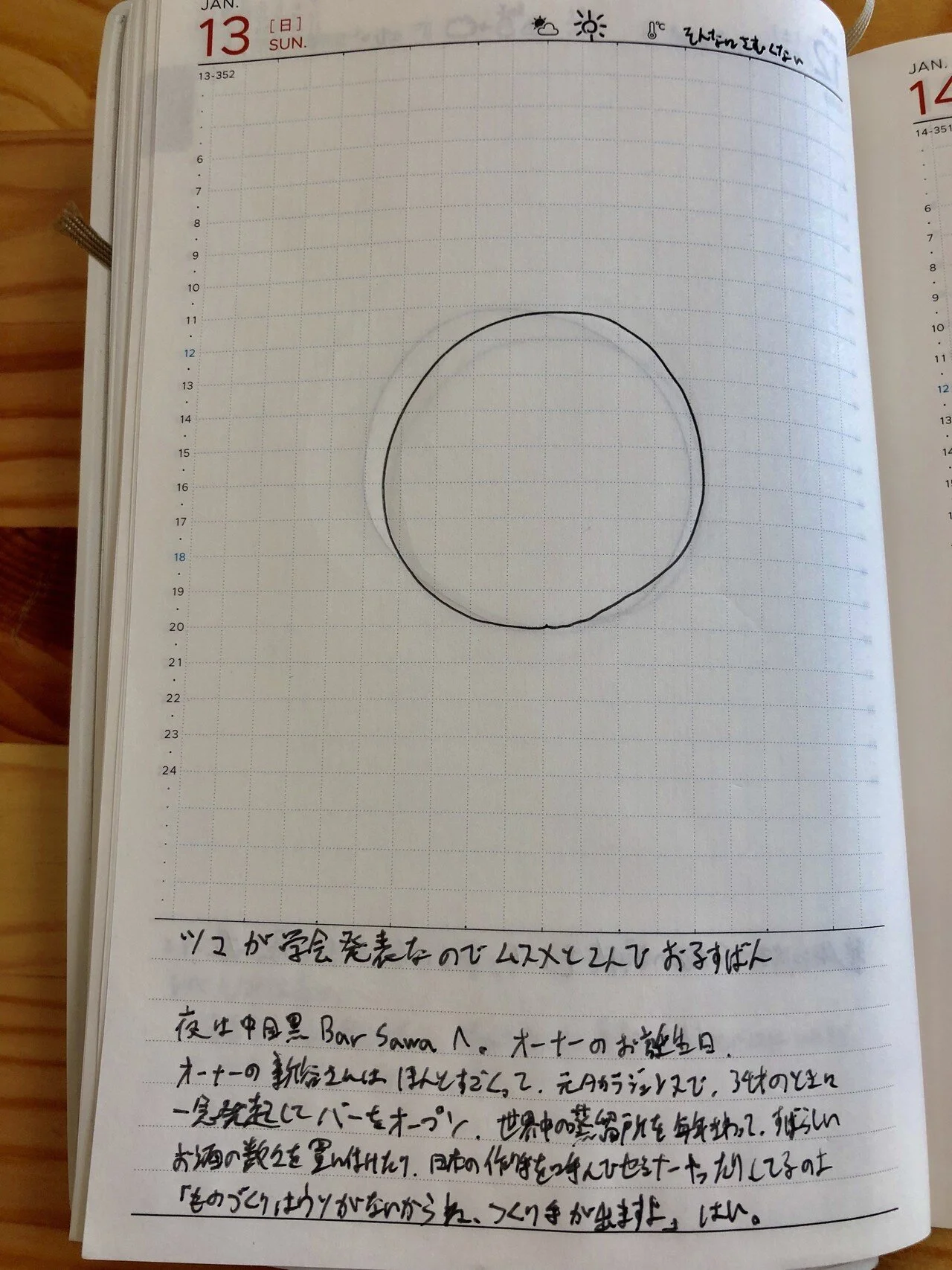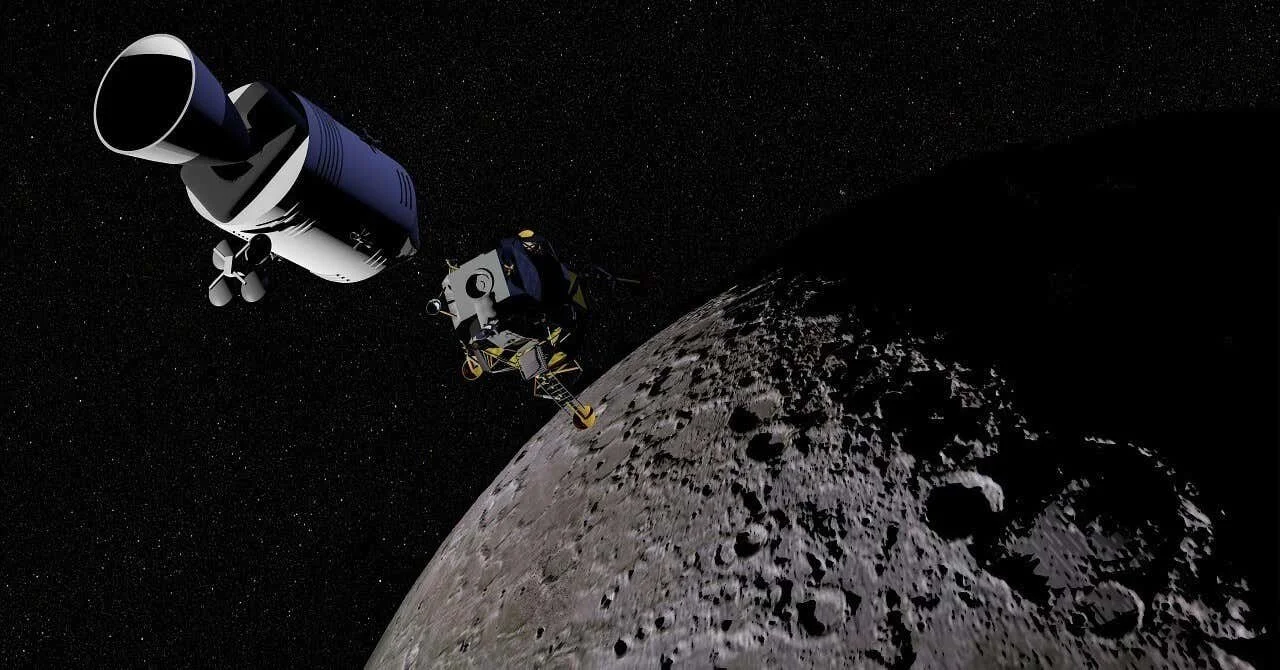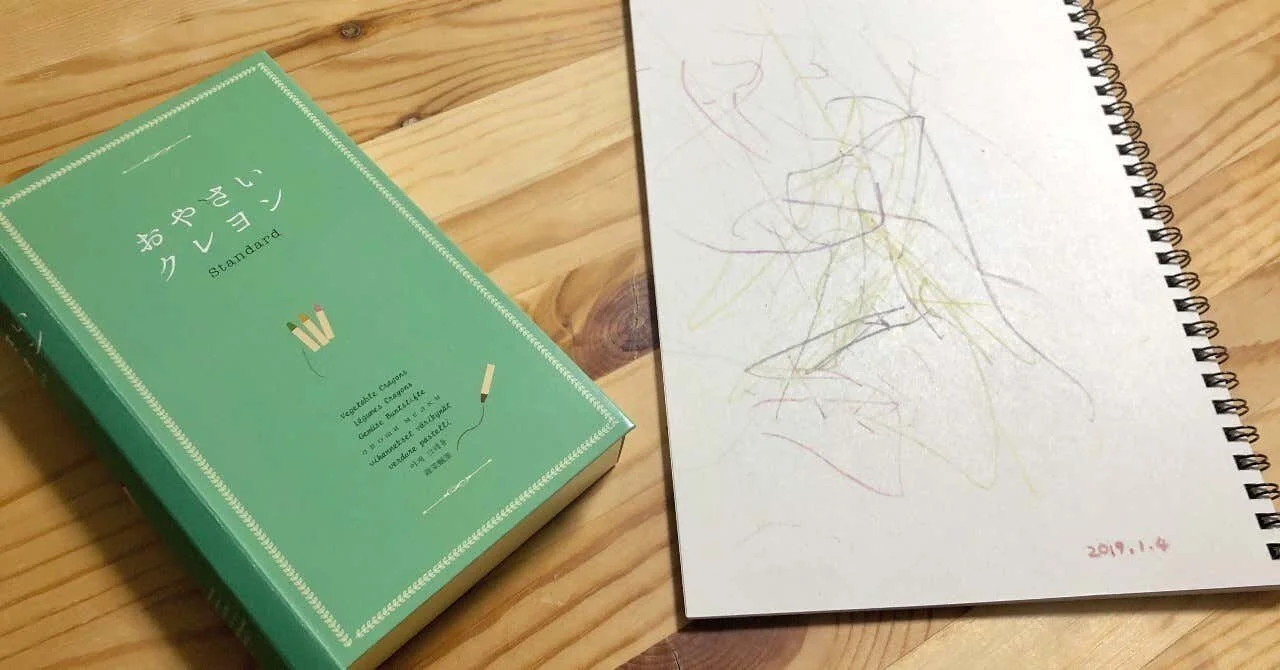仕事においては、必ずしも「好きなこと」じゃなくても「できること」にフォーカスして自分のやること考えていってもいいんじゃないすかってことを書いた昨日のnoteに対して、同じようなことを考えていたという友人から、じゃあ更に「やりたいこと」というのはどういう位置づけになるのだろう?という質問をもらった。
「やりたい」という気持ちは、もちろん自分の「好き」が起点となって生まれることもあるけど、「◯◯さんのために」って感じで誰かに貢献したい、自分の持てるものを与えたい贈りたいというのが起点なこともあるので、その意味で「できること」的な側面が強いこともありますねーというようなことをお返事として書いた。
僕が大学生の頃は今ほど「好きなことで生きていく」的風潮はなかったけど、「働く意味」とか「やりがい」みたいなのを探すのに悶々とするみたいな傾向はあったかもしれない。しかしそれも、あまり自己完結的に考えても仕方なくて、「求めに応える」を繰り返すうちに見えてくる部分もあって、特に僕の場合はそうだった。ろくすっぽ就活もせずに流れに乗っていまに至るなので。
あまりこう、学生とか新卒1,2年目のときに「働くとは…」みたいな問いに答えを出そうとしなくても、まぁ「できること」を積み重ねる間に見えてくるものがあるんじゃないの、自分で探すだけでなくて、働く中で誰かに見出してもらう面もあるよ、と。
responsibilityっていい言葉で、責任と日本語では訳されることが多いけど、response + ability、他者からの呼びかけ(calling)に応える力があるっていうことである。働く場面においては、自分が好きかどうかよりも、顧客や同僚からの自分に対する潜在・顕在の求め・期待に応えられるかどうかの方が大きいのではないかと思う。
わかりやすい代替指標として「お金」があって、まぁそれ以外でも良いのだけど、仕事に対する対価とか会社からの給与に対して、自分は見合う働きをできているかどうか。「新卒はまず営業で下積みな!」とマネジメント側が思考停止テンプレ配置するのは良くないと思うけど、最初のうちに「お客さんに払ってもらっているお金に見合う価値を返せてるか」を意識する経験はした方がいいと思う(それが「営業」でなくても担保できれば良いが営業がわかりやすい面はあるな…)。
で、話を冒頭の「やりたいこと」ってなんだろう、という問いに戻すと、自分の「好き」が起点でなくても、働く上でのやる気とかエネルギーというのは、他人のために湧いてくることは全然あるのであって、お客さんとか一緒に働く仲間のため、自分に対して何らかの期待をしてくれている人に応えたい、「だから、今これをやりたい」と、そういう機序での「やりたい」も全然あるよね。
まぁあんまり自分の好き・嫌いというシンプルな感覚を置いてけぼりにするとそれはそれでバランスが崩れるのだけど。